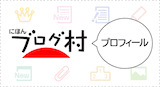最終更新日 2024年7月15日
広告
1、はじめに
身寄りのない【認知症の叔母】
(私の父の妹・1939年生まれ)は、
「特別養護老人ホーム」に入所しています。
私は叔母の保証人になっていますが、
「財産管理」をする余裕がありません。
特に「空き家」の管理に困っていました。
その旨を「日常生活自立支援事業」で
お世話になっている
「社会福祉協議会」に相談したところ、
「成年後見制度」の事を教えて頂き、
早速「申立て」することにしました。
私のように困っている方の
一助になれればと思い
「成年後見」の書類作成から
「申立て」までの紹介をします。
最後まで読んで頂ければ幸いです。

財産や権利を保護し、
生活を支援することを目的とした制度が
「成年後見制度」です
2、成年後見制度とは
(1)判断能力の不十分な方の財産、
権利の保護、生活の支援
①認知症、知的障害、精神障害などで
判断能力が不十分な方は、
財産管理や諸手続きを行うのが
困難な場合があります。
②判断が出来ずに契約して、
悪徳商法の被害にあう恐れがあります。
③このような判断能力が不十分な方の
財産や権利を保護し、
生活を支援することを目的とした制度が
「成年後見制度」です。
④「自己決定の尊重」
「残存能力の活用」
「ノーマライゼーション※」
の3つの
基本理念と「本人保護」の理念を
調和させることを主旨としています。
※ノーマライゼーションとは:
北欧諸国が始まりの社会福祉に関する
社会理念の一つで、障害者も、
健常者と同じような生活が
出来る様に支援するべき、
という考え方です。
また、そこから発展して、
障害者と健常者は、
お互いが区別されることなく、
社会生活を共にするのが正常なことで、
本来の望ましい姿であるとする考え方
としても使われることもあります。
またそれに向けた運動や施策なども
含まれます。
広告
3、成年後見制度を利用する時は
(1)自分で財産管理ができない時
(2)悪徳商法の被害にあわないために
(3)財産相続の手続きしたい時
①遺産相続者に重い障害があり
手続きができない時
(4)親族の支援が受けられない時
①障害者を子に持つ親が、
自分が死んだあとが心配な時

判断能力の不十分な方の財産、
権利の保護、生活の支援
4、法定後見制度
法定後見制度は、判断能力に応じて
以下の3つの支援内容があります。
(1)後見(成年後見人)
①精神上の障害で
(認知症、知的障害、精神障害など)
常に判断能力を欠いている方。
②申請には医師による鑑定が必要です。
③申立人(手続きをする人)は
本人、配偶者、4親等内の親族、
検察官、市町村などです。
④手続きの本人同意は不要です。
⑤本人の同意が不要で、
日常生活に関する行為以外の権限、
財産に関する全ての権限が
与えられます。
(2)保佐(保佐人)
①精神上の障害で
(認知症、知的障害、精神障害など)
判断能力が著しく不十分な方。
②申請には医師による鑑定が必要です。
③申立人(手続きをする人)は
本人、配偶者、4親等内の親族、
検察官、市町村などです。
④手続きの本人同意は不要です。
⑤民法13条1項所定の行為及び
申立ての範囲内で家庭裁判所が
定める特定の法律行為が本人の
同意不要で与えられます。
申立て範囲内で家庭裁判所が定める
特定の法律行為が本人の同意が必要で
与えられます。
(3)補助(補助人)
①精神上の障害で
(認知症、知的障害、精神障害など)
判断能力が不十分な方。
②申請に医師による鑑定は不要です。
③申立人(手続きをする人)は
本人、配偶者、4親等内の親族、
検察官、市町村などです。
④手続きの本人同意が必要です。
⑤申立て範囲内で家庭裁判所が
定める特定の法律行為の権限が
本人の同意が必要で与えられます。
申立て範囲内で家庭裁判所が定める
特定の法律行為が本人の同意が必要で
与えられます。
広告

5、任意後見制度
(1)本人があらかじめ、
任意後見人になってくれる人と後見内容
について任意後見契約を結んでおきます。
(2)本人の判断能力が不十分になった時に、
財産管理や身上監護を任意後見人が
代わって行う制度です。
(3)任意後見契約は、公証人による
公正証書で作成します。
(近くの公証役場で作成)
(4)任意後見人による援助の内容は、
本人の希望に応じて設定できます。

3つの支援内容があります
6、成年後見制度の流れ
*法定後見*
(1)家庭裁判所にて
「成年後見申立てセット」を入手
(2)申立てに必要な書類
①申立人:
・戸籍謄本
・住民票
②本人:
・申立書
・本人に対する照会書
・親族関係図
・診断書、鑑定連絡票
・戸籍謄本
・住民票
・登記されていない事の証明書※
・財産の裏付けとなる資料のコピー
・収入、支出に関する資料のコピー
登記されていない事の証明書:
本人に後見人がいない事を
東京法務局に証明してもらいます。
東京法務局からは「切手」の貼ってない
郵便で証明書が届きます。
③後見人候補者:
・候補者に関する照会書
・戸籍謄本
・住民票
(3)申立て人が必要書類を揃えて
家庭裁判所へ行き手続き
①家族、親族、後見人候補者が
成年後見になる場合
・家庭裁判所が成年後見の候補者の
適格性などを審査
・家庭裁判所が成年後見を選任
②家庭裁判所が選ぶ第三者が
成年後見になる場合
・司法書士等が選任されます。
*任意後見*
(1)本人と本人が選んだ後見人候補者が
二人で公証役場へ行き契約書を作成
(2)本人の判断力が低下した時
①任意後見監督人の選任手続き
②家庭裁判所が任意後見監督人を選任
広告
7、法定後見制度の利用にかかる費用
(1)収入印紙
①申立手数料:800円~2,400円
②登記嘱託費用:2,600円
(2)郵便切手
①審理中の通信費
・310円×3枚
・82円×10枚
・10円×10枚
・5円×2枚
・2円×10枚
・1,130円×1組
②保佐、補助開始の場合のみ
・1,072円×1組
広告
8、おわりに
「成年後見人」の選任までの
流れを紹介しました。
叔母の「成年後見人」が決まるまでに
約3か月かかりました。
特に提出書類が多く、
書き方もわからず
確認や謄本の取り直しなど
書類を揃えるのに時間がかかりました。
その中でも、
①「登記されていない事の証明書」は、
東京法務局からの証明書が
切手が貼ってない物が届き(受け取り人負担)
宛名が手書きで、差出人もゴム印で薄く
いたずら郵便かと思い、
「受け取り拒否」で返してしまいました。
その後東京法務局から電話があり、
切手代を負担しなければいけないと
聞きました。
②成年後見人の申立てをするのに
「親族の意見書」が必要でした。
私の場合は叔母からみて「甥、姪」が
私以外に4人いますので、
それぞれに「成年後見制度」利用の
可否などを書面で表した物を郵送、
回収するのに時間がかかりました。
以上のようにして「成年後見人」が
地元の司法書士に決まり
今後についての打ち合わせをして
ひとまず手続きが完了しました。
最後まで読んで頂き有難うございます。
9、関連記事