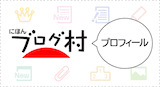最終更新日 2024年6月22日
広告
1、はじめに
12月は年の暮れで、
何かと慌ただしい時期で、
様々な行事もあり、
気持ちにゆとりがなく
忙しく過ぎていきます。
このような気持ちに
ゆとりがないときは、
ミスや事故が発生するものです。
いつもの月よりも落ち着いて
行動するように心がけたいものです。
以下に【12月】について紹介します。
最後まで読んでゆとりを持って行動し、
1年の最後を締めくくりましょう。

2、12月の別名
12月の別名:師走(しわす)
師走の由来・意味:諸説あります
①師である僧侶が、お経をあげるために、
忙しく走りまわる月だから
・師馳す(しはす)
・師走り月
②農作業を終える月から
「万事し果つ月(ばんじしはつつき)」
③1年を納めるつきから
「四季果つ(しきはつ)」
「為果つ(しはつ)
④春の訪れを待つという意味から
「春待月(はるまちづき)」
とも言われます。
*英語で12月:December(ディセンバー)
*12月の色:緑青(ろくしょう)
銅が酸化してできる錆びのような、
くすんだ「あおみどりいろ」のことです。
仏教伝来と共に日本に伝えられた鉱物の色で、
神社仏閣の屋根や、青銅の銅像などに
使われています。

3、12月の行事
12月1日:世界エイズデー
世界エイズデーは世界レベルでの
エイズのまん延防止と
患者・感染者に対する
差別・偏見の解消を目的に、
WHO(世界保健機関)が
1988年に制定したもので、
毎年12月1日を中心に、
世界各国でエイズに関する
啓発活動が行われています。
厚生労働省HPより引用
12月1日:映画の日
1896年(明治29年)
神戸市で日本で初めての映画が
上映されたのを記念して、
1956年(昭和31年)に
日本映画製作者連盟
(旧日本映画連合会)が制定しました。
12月7日頃:大雪
雪が降り、やがて大雪になる頃。
(大雪の詳細はこちらからどうぞ)
12月8日:事八日(ことようか)
年間の祭事、農作業の納めの日。
12月8日:針供養
事八日に折れたり、曲がったり、
錆びたりして使えなくなった針を
近くの神社などに納めて、
供養してもらう日。
広告
平均年収でも早期リタイア可能【The Ultimate Guide to FIRE For Japan】
12月10日:世界人権デー
1948年(昭和23年)12月10日、
第3回国連総会で
世界人権宣言が採択さえました。
これを記念して12月10日は
世界人権デーとなりました。
この日は、
国連を始めとして世界各地で
人権思想高揚運動が行われます。
世界人権宣言 世界人権宣言は,
基本的人権尊重の原則を
定めたものであり,
それ自体が
法的拘束力を持つものではありませんが,
初めて人権の保障を
国際的にうたった画期的なものです。
法務省HPより引用
12月21日頃:冬至
1年で最も日が短い日で、太陽が復活する日。
(冬至の詳細はこちらからどうぞ)
12月13日:正月事始め
正月の準備を始める日。
(正月事始めの詳細はこちらからどうぞ)
(年末大掃除はこちらからどうぞ)
12月13日~12月20日:お歳暮
お世話になった人に、
今年1年の
感謝の気持ちを込めて贈る品。
(お歳暮の詳細はこちらからどうぞ)
12月中旬~12月31日:年の市
年末に正月の飾り物や
正月用品を売る市のことで、
寺社の境内などで開かれます。
(年の市の詳細はこちらからどうぞ)
12月15日:年賀状の受付開始日

12月25日:クリスマス
クリスマスは約2000年前、
ベツレヘムの馬小屋で生まれた
イエス・キリストの誕生日を祝う
「降誕祭」です。
キリスト教の国では、
復活祭と並ぶ大切な祭日で、
朝から協会でミサが行われます。
12月28日:仕事納め
1年間の仕事を締めくくる日。
(仕事納めの詳細はこちらからどうぞ)
12月31日:大晦日
1年最後の日
(大晦日の詳細はこちらからどうぞ)
4、12月の月神様
12月の月神様は、
大師さま(ダイシサマ)です。
冬至に来て、福をもたらしてくれます。
ご利益:来福
櫛名田比売(クシナダヒメ)
ヤマタノオロチの餌食になるところを
スサノオに助けられ、妻になる。
ご利益:縁結び
広告

5、12月が旬の食べ物
(1)野菜類
①キャベツ
②水菜
③小松菜
④大根
⑤長ネギ
(2)果物類
①西洋梨
②ミカン
③リンゴ
④レモン
⑤ゆず
(3)魚介類
①アンコウ
②金目鯛
③たら
④ぶり
⑤牡蠣
6、12月の花と花言葉

山茶花(さざんか):謙譲

寒椿(かんつばき):愛嬌

葉牡丹(はぼたん):祝福

千両(せんりょう):富貴

南天(なんてん):機知に富む

ポインセチア:祝福、幸運を祈る、聖夜

石蕗(いしぶき):困難に負けない
7、時候の挨拶
(1)書き出し
①初冬の候
②寒冷の候
③初雪の候
④歳末の候
⑤寒さも日毎に増します
今日この頃
⑥今年もいよいよ
押し迫ってまいりました
(2)結び
①寒さが厳しくなってきましたが、
体にはお気をつけて下さい。
②忙しい年末ですが、
くれぐれもお体を大切にして下さい。
③寒さが続いておりますが、
風邪などひかないようご自愛ください。
④ご家族そろって、
健康で新年を迎えられますよう
願っております。
⑤来年も素晴らしい年でありますよう
お祈りします。
⑥ぜひともよいお年を
お迎えくださいませ。
広告
8、おわりに
12月は、
飲食をする機会が多い月だと
思いますが、
暴飲・暴食をしないように
十分注意しましょう。
厳しい寒さが続く時期ですので、
風邪などを引いて
折角の正月を台無しにしないように
して下さい。
私は、
年末の暴飲暴食で風邪と胃腸炎で、
正月に辛い思いをしたことがあるので
同じようにならないようにして下さい。
最後まで読んで頂き有難うございます。
参考書籍①:PHP研究所発行
知れば納得!暮らしを楽しむ12ヶ月のしきたり
参考書籍②:株式会社神宮館発行
暮らしのしきたり12ヶ月
うつくしい日本の歳時と年中行事
参考書籍③:主婦と生活社発行
神さまがやどる暮らしのしきたり
開運BOOK
参考資料:ウィキペディア
にほんブログ村