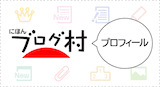最終更新日 2024年7月16日
広告
1、はじめに
「自宅で自由に働いて
収入を得ることができる」
私の理想的な働き方です。
過去には馴染みがなかった
仕事ですが、
最近は飛躍的に増加しています。
そのような
「自宅で自由に働いて
収入を得る仕事」
を紹介してくれる株式会社Wizの
サイトがあります。
そのサイトは
コールシェア
です。
以下に紹介しますので、
「無料で在宅ワーク」を始める
第一歩にして下さい。

全て在宅で行うことができる
「在宅コールセンターの仕事」サイトです
2、コールシェアとは
(1)コールシェアは「登録から仕事開始」まで、
全て在宅で行うことができる
「在宅コールセンターの仕事」サイトです。
(2)「日本一稼げる在宅ワーク」を目指して、
仕事だけでなく 研修・教育にも力を
入れてくれます 。
(3)時給換算も平均で1,400円を超え、
6人に1人が月収10万円を超えるなど
「稼げる在宅ワーク」として
多くの方が活躍しています。
コールセンター業務とは:
インバウンド業務とアウトバウンドに分けられます。
(1)インバウンド:
お客さまからかかってきた電話に応対する業務です。
電話の内容は、問い合わせ、申し込み、質問、意見等です。
(2)アウトバウンド:
営業的な電話で商品やサービスの売り込みをします。
広告
3、コールシェアの特長
(1)自由な働き方ができる
(2)好きな時間に勤務ができる
(3)6人に1人が月収10万円を超える
(4)スキルや資格がなくてもできる在宅ワーク
(5)登録・初期費用は無料
(6)必要な機材の準備も前面サポート
(7)初心者でも教育担当が
丁寧に教えてくれる
(8)働いている方の月収例
①フルタイムで働く方:
1日6h × 月20日勤務=34万
②隙間時間で勤務する主婦の方:
1日4時間 × 14日勤務=8~9万
⑨急遽のシフト変更もOK

丁寧に教えてくれます
4、仕事開始の流れ
仕事開始後は常に教育担当が
待機してくれるので
徹底したサポートを受けられます!
- (1)会員登録
- ①コールシェア公式サイトの
「無料会員登録フォーム」に進む
②必要事項を入力し、
会員登録してください。

- (2)ヒアリング
- ①あなたの希望条件の
簡単なヒアリングあります。

- (3)仕事紹介
- ①ヒアリング後、
あなたの適正に合う
仕事を紹介してくれます。

- (4)仕事開始
- ①研修を受けて仕事開始です。

広告
5、おわりに
コールシェア
の仕事は
「在宅ワーク」という特性のため、
ある程度のITリテラシーが求められます。
ITリテラシーとは:
通信・ネットワーク・セキュリティなど、
ITにひも付く要素を理解する能力、
操作する能力という意味です。
コールシェア
の仕事は
①主婦やコールセンターで
働いた経験がある方。
②日中に出来る在宅ワークを
探している方。
に特におすすめです。
とはいえ、
初心者でも安心して働けるように
常に教育担当が待機して、
徹底したサポートを受けられますので
まずは、
無料会員登録
から始めましょう。
最後まで読んで頂き有難うございます。
参考資料①:シェアコールナビ.jp
参考資料②:ウィキペディア
6、関連記事
仕事に関するご利益のある神社(東北~北陸・静岡)
仕事に関するご利益のある神社(東海~九州)
仕事に関わる四字熟語