最終更新日 2024年2月28日
広告
1、はじめに
お正月を挟んだ、
12月8日と2月8日の二日を
「事八日」といいます。
このうちのどちらかを【事始め】とし、
もう一方を【事納め】としています。
この場合の「事」とは、
神事や農事を表す言葉です。
この「事」が正月に行われる神事ならば、
12月8日が【事始め】になり、
2月8日が【事納め】になります。
また「事」が農事ならば、
2月8日が 【事始め】 になり、
12月8日が 【事納め】 になります。
全国的に統一された行事では
ないので、聞きなれない言葉ですが、
ここに紹介します。
ぜひ話題のタネにして下さい。
広告
2、事始めの由来
【事始め】は2月8日にしても、
12月8日にしても「物忌み※」の日に
あたります。
※物忌みとは:
ある期間、行動、食事、言動などの
日常的な行為を慎み沐浴などをして、
心身の穢れを避けること
この日は、
徘徊する魔物たちを退治や、
歓迎することや
針を使うことが戒められてきました。
2月8日を【事始め】にする説は諸説ありますが、
①「武御雷(たけみかづち)の神※2」が
2月8日に出陣し、
12月8日に帰陣したことからとの
説が有力です。
※2武御雷の神とは:
日本神話に登場する神様で、
雷神、剣の神様と言われ、
茨城県鹿嶋市にある鹿島神宮の主神として
祀られています。
②農作業の準備が2月から始まり、
12月に農作業の神事が終わると言う説
などがあります。
反対に12月8日を【事始め】として、
2月を【事納め】とするのは、
「事」が「正月」に関する行事と
考えるからです。
また、12月8日から2月8日までは
収穫が終わり、次の農事が始まるまでの
「物忌み」の期間とされています。

3、事始めの行事
【事始め】には日本各地で
様々な行事が行われます。
(1)一つ目小僧
疫病神が家を訪れて悪さをするので、
籠やざるなど細かい目の道具を玄関に置いて
侵入を防ぐ
(2)【事納め】には
「ハリセンボン」という魚が
やってくる日とされ、
浜辺に打ち上げられた
「ハリセンボン」を拾い
厄除けとする習わし
(3)わらで大きなムカデや草履を作り
隣の地区との境界線に飾り
厄除けをする習わし
などがあります。
広告

4、針供養

2月8日と12月8日は【針供養】の
日でもあります。
(1)針供養とは
①裁縫が上手になることと、
ケガをしないことを願って
豆腐やこんにゃくなどの柔らかい物に、
古くなったり、折れたりした針を刺して、
神棚に供えたり、川に流したりします。
②地域によっては、2月8日と12月8日の両日
行う所もあれば
どちらか一方の所もあります。
③この日は針の仕事で
使われている針を休め
裁縫の仕事を休む日になっています。
(2)針仕事の減少
①最近では家庭での針仕事を行う機会が減り
針供養を見かける機会も
少なくなりましたが、
服飾関係の現場では今でも
針供養が行われています。
針供養で有名な神社:
和歌山県の淡島神社(あわしまじんじゃ)は
裁縫の神様が祀られていることから
針供養に結びついたとされています。
また、婦人病を治してくれる神社としても有名で
人形供養なども行われます。
(3)日本各地の針供養
①北陸地方では「針歳暮(はりせんぼ)」と
呼ばれる行事があり、
この日は針に一切触れずに、
まんじゅうなどを食べたり、
贈ったりする習わしがあります。
②長野県では針を豆腐に刺し、
神棚にあげたり
縁の下に投げ入れたりする
習わしがあります。
広告
5、おわりに
【事始め】の日は、
各地で様々な行事が行われて、
その意味の捉え方が異なりますが、
生活していく上で基になる
大切な日です。
そんなことを考えながら
【事始め】の
一日を過ごしたいものです。
最後まで読んで頂き有難うございます。
参考書籍:株式会社神宮館発行
暮らしのしきたり12ヶ月
参考資料:ウィキペディア
6、関連記事
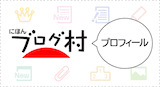


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39d178ac.161ad367.39d178ad.a465508c/?me_id=1396573&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyakusho%2Fcabinet%2Farerupita%2Fareru_1set_202304.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

