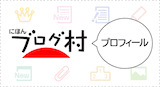最終更新日 2023年10月11日
広告
1、はじめに
【野村克也】の数多くの名言の中に
指導とは教え込むのではなく
気づかせること
という言葉があります。
この言葉は、
野球選手だけでなく、
我々一般人にも当てはまります。
仕事や子育ての場面で
直面することがあります。
そんな時に、
少しでも役立てて頂きたいと思い、
紹介します。
ぜひ参考にしてください。

「野村ノート」という物に書き綴った
メモにあります。
2、野村ノート
【野村克也】の指導における原点は、
「野村ノート」という物に書き綴った
メモにあります。
現役時代からずっと続いていたそうです。
きっかけとなったのは、
「南海ホークス」の選手時代です。
【野村克也】の現役時代は、
現在と違って理論的に指導できる、
「監督、コーチ」がほとんどいなくて、
どちらかと言えば
「根性論」的な指導でした。
その顕著な例が「鶴岡一人監督」です。
【野村克也】の著書の中で
何度も登場しています。
エピソードとして紹介せれているのが、
キャッチャーとしてピッチャーに
「サイン」を出しますが、
出した「サイン」で打たれた時
「怒鳴られる」だけで、
教えを乞うても「自分で考えろ」
「勉強しろ」としか言われなかったそうです。
だから、
「自分で考え、自分で研究」するしか
ありませんでした。
ここから「相手の弱点、クセ」などを
メモとして残したのが
「野村ノート」の始まりです。
「野村ノート」は監督になってからの
試合前のミーティングで使って
いたそうですが、
内容は、野球選手と言うより、
社会人として
いかにあるべきかという話しが
多いかったそうです。
「プロ野球選手」になるほどの選手なので、
小さい頃から周りにちやほやされ
「お山の大将」のような選手が
ほとんどなので、
社会人としての意識を高めるための
話が中心でした。
「野村ノート」は、
このような【野村克也】の
「指導法」が蓄積された貴重な資料です。
スポンサードリンク
3、指導とは・・気づかせること
【野村克也】の指導法の一つでもあり
名言でもある言葉に
指導とは教え込むのではなく
気づかせること
という方針があります。
監督時代に自分から選手に
「このようにしなさい」と
言ったことは
ほとんどなかったそうです。
しかしながら、コーチの中には、
選手に付きっきりで「手取り足取り」
指導するコーチがいましたが、
それには否定的です。
コーチは、
一般社会で言えば「中間管理職」で
「上司には認められたいし、
部下にはしっかり指導したい」ということで
必死です。
それだから「手取り足取り」の
指導になりがちです。
ただ、このような指導で「将来を嘱望」
された選手が本来もっている素質を
つぶされて活躍しないまま「プロ野球界」を
去って行くケースが多々あります。
このような事があるので
【野村克也】は
選手に教え込むことがありませんでした。
そこで、選手に気づかせるために
いわゆる「ボヤキ」をしました。
ベンチ内で試合の展開とか、
相手選手のこと
などを選手に聞こえるように
「ボヤキ」ました。
特に相手選手をほめることにより、
攻略法を
気づかせるようにしました。
何故、
気づかせることが必要なのか?
自著「野村の人生ノート」には、
「指導される本人が必要だと思わなければ、
指導者のアドバイスが役に立たない」
「必要と言うのは、選手の気づき」
「指導者は環境づくりをする」
という内容が書かれています。
このような考えがあるから
指導とは教え込むのではなく
気づかせること
という名言が生まれました。

攻略法を
気づかせるようにしました野球
4、まとめ
指導とは教え込むのではなく
気づかせること
という言葉は、
一般の社会人としても当てはまります。
上司として指導する立場の人だけでなく、
部下として働く場合も、
逆の捉え方をして
「1から10まで」教えてもらうのではなく、
自分で考えて仕事をしなければ
全く成長できません。
自ら気づくようにしなければいけません。
そのためには、仕事をする上で
「好奇心を持ち、積極的」に
行動することが必要です。
この名言は、
あらゆる気づきの大切さを
教えてくれる言葉ではないでしょうか。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
(参考文献=日本文芸社発行:野村克也・野村克則著
野村の「人生ノート」)
広告
5、関連記事