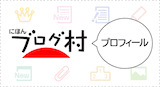最終更新日 2024年6月4日
広告
1、はじめに
夏のレジャーと言えば
何と言っても「山・川・海」です。
今回は、
その中で【山開き・川開き】
について紹介します。
毎年7月1日頃「日本各地」で
「山や川」での遊びが解禁する
【山開き・川開き】が行われます。
それぞれ「どんな意味」や「歴史」
があるのかを知り
「山や川」で
夏のレジャーを楽しんで下さい。

2、山開き
【山開き】と言えば何と言っても
「富士山」です。
「富士山」の【山開き】は
毎年7月1日ですので
【山開き】は「夏」の行事のように
思われますが、
3月~6月の間にも多くの山で【山開き】が
行われます。
日本の「山」は、
昔から「神霊」が宿るとされて
「山」を崇める「山岳信仰」が
盛んに行われてきました。
そのため「神仏」がまつられている
「山」には、
山伏(やまぶし=山野で修行する僧)や
行者(ぎょうじゃ=仏道を修行する人)しか
入山できませんでした。
それを春~夏の一定期間は禁が解かれ
一般の人も入山できるようにしました。
「山開き」は一般の人に
「登山」や「入山」を
許可する日で「開山祭」が行われ
一般の登山客の「安全」を祈願する
「神事」が行われます。
「富士山」の【山開き】では
白装束
(しろしょうぞく=
修験者などが着る白ずくめの服装)に
金剛杖
(こんごうづえ=
登山・巡礼者が持つ白木の杖)を
持った人々が
「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」と
唱えながら「山」に登ります。
「六根清浄」とは
①眼(根):視覚
②耳(根):聴覚
③鼻(根):嗅覚
④舌(根):味覚
⑤身(根):触覚
⑥意(根):意識
の6器官を清らかにすることです。
「山」に登る時に
「六根清浄」と唱えるのは
「山」の自然と一体になり
日常の生活で汚れた「六根」を清らかにし
「心を無」にすると言う
意味合いがあります。
「どっこいしょ」とは「六根清浄」が
変化したものだと言われています。
【山開き】の起源は江戸時代で、
一般の人に「山岳信仰」としての
登山が許されるようになりました。
その頃から
「富士山・人気」は絶大でしたが、
簡単に行けませんでした。
そこで富士吉田の本殿から
「神様を分けて祀る」ことをして
小さな「山」を人工的に作り
そこに小さな「浅間神社」を建てて
「富士山詣」の代わりにしていました。
【山開き】があれば
「閉める」日もあります。
それを「山終い」と言います。
「開山祭」とは逆の
「閉山祭」が行われ
「今年の安全御礼」と
「来年の安全祈願」が
行われます。

3、川開き
【川開き】とは「川での納涼」が解禁され、
水泳シーズンが始まることを祝い、
同時に水難防止の祈願が行われます。
多くの場合が7月1日に
花火を上げて祈願します。
江戸時代の「隅田川」では
「旧暦」の5月28日~8月28日
までの3か月間は「納涼期間」と
決められていました。
【川開き】の始まりは
1733年に「大飢饉」や
「疫病」による死者の供養と
疫病退散を祈願して
「水神祭」を行ったのが始まりです。
その時に余興として打ち上げ花火を
献上したことが人気となり
現在まで続く花火大会の
ルーツになっています。

4、おわりに
【山開き・川開き】と聞くと
夏のレジャーの始まりという
イメージがあり心がウキウキします。
【山開き・川開き】は現在では
娯楽的要素が強いのですが
元々は「安全・無事」を願う
「神事」から始まった
「神聖」な日です。
現在でも「山や川」での
一般の人の事故がよくあります。
昔の人が「山や川」を
「神聖視」した思いを
「山や川」でのレジャーの前に思い出し
「安全・無事」を考え
【山開き・川開き】を
楽しんでください。
最後までお読みいただき有難うございます。
参考書籍:PHP研究所発行
知れば納得!暮らしを楽しむ12ケ月のしきたり
参考資料:Wikipedia
5、関連記事