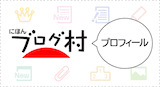最終更新日 2024年7月21日
広告
1、はじめに
【大暑】(たいしょ)】は
「二十四節気」の一つで毎年7月23日頃です。
2024年は7月22日(月)です。
【大暑】という通り、
1年で最も暑さが厳しい時期です。
夕立や夏の豪雨の時期でもあります。
そんな【大暑】について紹介します。
ぜひ「話題のタネ」にして下さい。

2、大暑の意味
【大暑】とは文字通り、
ますます「暑さ」が厳しくなる頃で、
安定した天気の良い日が続き「暑さ」の
ピークをこれから迎える頃で
夏の真っ盛りという意味があります。
【大暑】は俳句の「夏」の季語や
手紙の時候のあいさつや
暑中見舞いにも使われています。
また、最近は年々「暑さ」が厳しくなってきて
「暑さ」を表す「気象用語」もテレビなどで
「今日は〇〇度を超える〇〇日でした」
と紹介されることがよくあります。
そこで、
その「気象用語」について紹介します。
①猛暑日
最高気温が35度を超えた暑い日のこと。
②真夏日
最高気温が30度を超えた日のこと。
③夏日
最高気温が25度を超えた日のこと。
④熱帯夜
最低気温が25度以上の日のこと。
このように見ますと昔はあまり経験のなかった
「猛暑日」という言葉をよく聞くようになり、
「地球温暖化」が進んでいることが
よくわかります。
広告
3、大暑の3つの候と暑さを表す言葉
(1)【大暑】は7月23日頃ですが、
次の節気の「立秋」までの約15日間を
表す場合もあります。
この約15日間を
約5日ごとに三つの候(こう・時期)に分け
気象や動植物の変化を短い言葉で表したものを
七十二候と言います。
三つの候は
①初候(しょこう)
②次候(じこう)
③末候(まっこう)
になります。
また、変化を表す言葉は
中国伝来のものもありますが、
伝来後に日本風に変化したものもあります。
【大暑】の三つの候は以下になります。
①初候:7月23日頃~27日頃
この時期を表す言葉:
桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)

意味:桐の花が実を結び始める頃。
日本の風土気候に適している桐材は、
昔から家具や道具として
大切なものでした。
②次候:7月28日頃~8月1日頃
この時期を表す言葉:
土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)

意味:土がじっとりとして
蒸し暑くなる頃。
溽暑(じょくしょ)とは、
熱気がまとわりつくような
蒸し暑さを表す言葉です。
③末候:8月2日頃~7日頃
この時期を表す言葉:
大雨時行(たいうときどきにふる)

意味:時々激しい雨が降る頃。
大雨(たいう)とは、
夏の終わり頃の集中豪雨や
夕立のこと。
入道雲が夕立になり乾い大地を
潤します。
(2)【大暑】にちなんで「暑さ」を
表す言葉を紹介します。
①極暑(ごくしょ)
極めて暑いこと。
最近の異常な暑さを表現する。
②酷暑(こくしょ)
非情に暑いこと。猛烈な暑さ。
厳暑(げんしょ)とも言います。
③激暑(げきしょ)
真夏の激しい暑さのこと。
劇暑とも言います。
④炎暑(えんしょ)
真夏の焼け付くような暑さのこと。
⑤溽暑(じょくしょ)
湿気が多く蒸し暑いこと。
⑥運気(うんき)
湿気が多く蒸し暑いこと。
⑦暑熱(しょねつ)
夏の炎天下の暑さのこと。
⑧旱暑(かんしょ)
日照りで大変暑いこと。
聞いただけで
「暑く」なりそうな言葉ですね。
(3)その「暑さ」対策として昔から
家の前や庭先、道路、ベランダ等に水を撒く
「打ち水」が行われています。
「打ち水」により実際に温度が下がり
涼しく感じるのでおススメです。
また「打ち水」のイベントも
各地で行われています。
そのイベントの一つに
下記のイベントがあります。
参加してみてはいかがでしょうか。
http://uchimizu.jp/
(打ち水大作戦のホームページ)
打ち水大作戦のHPをリンク先として引用

4、大暑の頃の体に良い食べ物
【大暑】の日は
「天ぷらの日」と言われ
「天ぷら」を食べると
良いとされています。
その他【大暑】の頃の代表的な
食べ物は次になります。
①うなぎ(土用の丑)
夏の暑い時期を乗り越えるために
ビタミンやDHAなどを多く含み栄養価の高い
うなぎを食べます。
「土用の丑の日」にうなぎを食べるのは
「平賀源内」の発案と言う説もありますが
「万葉集」にも登場しています。
②うどん
消化吸収が良く、疲労回復、食欲がない時でも
食べやすい。
③梅干し
疲労回復、塩分補給、食欲不振の解消、
消化吸収も良い。
④うり類
きゅうり、すいか、ゴーヤなど。
体の熱を冷まし、むくみの防止になります。
⑤牛肉
タンパク質、ヘム鉄、ビタミンB2が摂れ
スタミナがつきます。
⑥しじみ
昔から「土用しじみは腹薬」と言われるほど
栄養価が高い。
以上の物を食べて「暑さ」に勝ちましょう。

5、この時期注意すること
この時期は記録破りの
最高気温を記録するなど、
体調管理や紫外線の対策に
注意したい時期です。
特に熱中症には注意して、
こまめな水分補給を
心掛けたいものです。
6、おわりに
【大暑】の頃は「海、山、川」のレジャーに
最適な時期です。
最適な時期とはいえ、
1年で一番「暑い」時期なので、
無理をしないで
休養もしっかりとって、その後に
「ひと夏の楽しい思い出」を
作って下さいね。
最後までお読みいただき有難うございます。
参考書籍:株式会社ナツメ社
まいにち暦生活・日本の暮らしを楽しむ365のコツ
参考資料:Wikipedia
広告
7、関連記事
7月の別名、行事など盛りだくさんの話題のタネ