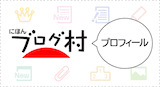最終更新日 2023年12月19日
1、はじめに
【三国志】より人の生き様に関する「故事」
7選を紹介します。
ぜひ、参考にして下さい。
広告
*三国志とは
魏(ぎ)、呉(ご)、蜀(しょく)の
三国が争っていた歴史を書いた歴史書で、
信頼性に乏しいことは、極力使っていません。
撰者は西晋の陳寿(ちんじゅ)です。
*主な登場人物
①劉備(りゅうび):
蜀漢(しょくかん)の初代皇帝
②関羽(かんう):劉備、張飛と
黄巾の乱から行動を共にし、
蜀の建国に尽くした人物
③張飛(ちょうひ):劉備、関羽と
黄巾の乱から行動を共にし、
蜀の建国に尽くした人物
④諸葛孔明(しょかつこうめい):
劉備に仕え、
天才軍師として活躍
⑤曹操(そうそう):
魏の建国に尽力し、
乱世の英雄とされる人物
⑥呂布(りょふ):武芸を極めた武将

*三国主な年表
| 西暦 | 魏での出来事 | 蜀での出来事 | 呉での出来事 |
| 220 | 曹丕が魏の文帝に | ||
| 221 | 孫権、魏に臣従する | 劉備が帝位につく | 孫権、呉王 となる |
| 文帝、呉を攻める | 劉備、陸遜に大敗 | 孫権、独自に 年号 | |
| 223 | 曹仁が呉に破れる | 劉備死す | 蜀と同盟。 |
| 224 | 文帝、呉を攻める | 呉の使者が来訪 | 徐盛が魏を 退ける |
| 倭女王が遣使 | |||
| 241 | 呉の侵攻を防ぐ | 蔣琬が進軍する | 魏と対峙する |
| 243 | 倭女王卑弥呼が遣使 | 姜維が大将軍に | 顧雍、死す |
| 244 | 曹爽が漢中で敗退 | 費禕が魏軍を退ける | 陸遜が丞相 となる |
| 250 | 呉の混乱に乗じて攻撃 | 姜維が西平へ進軍 | 孫亮が太子 |
| 252 | 呉の南郡を攻める | 孫権が死す | |
| 253 | 呉軍と攻防を繰返す | 費禕が刺殺される | 諸葛恪が 殺される |
| 263 | 蜀を平定 | 蜀は滅亡 | |
| 呉を滅ぼし統一 | 魏は滅亡 |
スポンサード・リンク
2、故事
①鶏肋
(けいろく)
意味:鶏のあばら骨は、
食べても腹の足しになるほどの
肉がついてないが、
捨ててしまうのには、
もったいないというところから、
役には立たないが
捨ててしまうには、
惜しいという意味。
エピソード:曹操が
鶏のあばら骨を食べながら、
「漢中地方は欲しいと思うが、
劉備には勝てそうもない」と
考えていたところ、
夏侯惇(かこうとん・後漢末期の武将)から
今後の計画を尋ねられました。
そこで曹操は、「鶏肋」と答えました。
意味がわからない夏侯惇は、
曹操に仕えている、
楊修
(ようしゅう・後漢末期の政治家)に
尋ねると
「鶏肋には肉はないが
捨てるのにはもったいない、
漢中地方はそういう土地です」と
答えました。
②死せる孔明生ける仲達を走らす
(しせるこうめいいけるちゅうたつをはしらす)
意味:優れた人物は、
生前の威光を備えていて、
死後も生きている人々を
恐れさせることの例え。
エピソード:諸葛孔明が
魏の司馬仲達
(しばちゅうたつ・後漢末期の政治家、武将)と
対戦中に亡くなったため、
蜀軍は引き返そうとしました。
司馬仲達にも「諸葛孔明の死」の情報が入り、
追撃しました。
しかし、
諸葛孔明の死ぬ前の命令により、
反撃に転じたため、
司馬仲達は、
諸葛孔明が
まだ生きているのだと勘違いし、
恐れをなして、逃げ帰りました。
③雪中の筍
(せっちゅうのたけのこ)
意味:得難い物を得たり、
ありえないことが起きる例え。
エピソード:呉の孟宗
(もうそう・呉の政治家)は、
病気で寝ている母が、
冬にも関わらず筍を食べたい
と言ったため、
あちこち探しまわりました。
冬の雪で埋もれた竹林に
筍などあるはずもありません。
「何とかしなければ」と
歩いていると、
雪の中から筍が出てきました。
喜び勇んで帰り母に筍を食べさすと、
元気を取り戻しました。
*孟宗竹の名前の
由来にもなっています。

④天に二日無く、土に二王無し
(てんににおうなく、どににおうなし)
意味:天に太陽が一つしかないように、
一つの国に君主は二人もいらない。
エピソード:荊州
(けいしゅう・現在の湖北省一帯)
を手中にした劉備に対して、
諸葛孔明が、
「君主になるべき人が、
二人いてはいけない、
もう一人いる
益州(えきしゅう・現在の雲南省)の
劉璋(りゅうしょう・後漢末期の群雄)を
倒さなければいけない」と言った言葉です。
⑤読書三余
(どくしょさんよ)
意味:読書や勉強をするのに
適するのは、
季節では冬、一日では夜、
天候では雨が好都合の
三つの余暇。
エピソード:魏の董遇
(とうぐう・儒学者、政治家)に
教えを乞う若者がいました。
董遇は「本は必ず100回以上読みなさい、
100回以上読めば意味がわかるはず」と
言いました。
若者は「そんなに読む暇がありません」と
答えました。
それに対して董遇は
「人の生活には、冬、夜、雨の日の
三つの余暇があるので、
使うようにしなさい」と教えました。
⑥鳥の将に死せんとするや、其の鳴くや悲し
(とりのまさにしせんとするや、そのなくやかなし)
意味:鳥が死のうとしている時の
鳴き声は
人の心を打つほど悲しげである。
エピソード:病気のため
寝たきりになっていた劉備は、
自分の死を悟り、
諸葛孔明に今後のことを託した後、
亡くなりました。
その死に際の悲哀を表現した言葉です。
⑦白眼視
(はくがんし)
意味:冷たい目つきで見る事。
冷たく扱う事。
エピソード:酒を飲みながら
世俗を離れた哲学の話をする
竹林の七賢(ちくりんのしちけん)の
リーダー阮籍(げんせき・思想家)が、
じぶんの気に入っている人に対しては、
黒目で歓迎の気持ちで接したのに対して、
自分の気に入らない人に対しては、
白目をむき出しにして
接した事からでた言葉です。
広告

3、おわりに
【三国志】より人の生き様に関する
「故事」7選を紹介しました。
「故事」一つ一つに
深い意味があります。
よくかみしめて頂き、
生き方の参考になれば幸いです。
またこれを機に【三国志】の世界に
足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。
最後まで読んで頂き有難うございます。
参考書籍:株式会社HK INTERNATIONAL VISION発行
三国志故事成語辞典
参考資料:ウィキペディア
4、関連記事
①三国志より人間関係に役立つ故事
10選はこちら
②三国志より人物に関する故事
9選はこちら
③三国志より行動に関わる故事
8選はこちら
④三国志より志や戒めに関する故事
8選はこちら