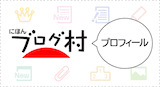最終更新日 2024年6月7日
広告
1、はじめに
【半夏生(はんげしょう)】は、
かつては「夏至」から約10~11日経過した
日でしたが、
現在では天球上の「黄経※」100度の点を
太陽が通過する日となっていて
毎年7月2日頃になります。
2024年は7月1日(月)です。
※黄経:黄道座標では、
天球上の緯度と経度にあたるものとして
黄緯と黄経で表します。
黄緯は地球の公転面の天球上への投影である
黄道を0度、
地球の公転面に垂直な方向を90度として
表します。
黄経は「春分」を0度として、
太陽の黄道上の見かけの運動方向と
同じ方向に向かって値を増やして
春分に戻る360度まで数えます。
つまり夏至は黄経90度、「秋分」は黄経180度、
「冬至」は黄経270度となります。
地球の歳差運動
(自転している物体の回転軸が、
円を描くように振れる現象)によって
春分点の位置が黄道上を移動していくため、
黄経の値は歳月とともに変化します。
【半夏生】は1年に9回ある
「雑節」の一つです。
この時期は一般的には
「田植えが終わり、梅雨が明ける頃」と
されていますが、
実際にはその年の天候や地方によって
異なります。
では【半夏生】とはどのような
意味があるのでしょうか?
以下に紹介します。
ぜひ参考にして下さい。

2、半夏生とは
「半夏」とは生薬となる植物の
烏柄杓(からすびしゃく)のことをいいます。

烏柄杓:
サトイモ科の多年草。
畑などに生え、高さ約20センチ。
葉は3枚の小葉からなり、
長い柄の中ごろと上端とに1個ずつ
むかごをつけます。
7月の初め頃花をさかせますが、
葉っぱの一部分が白くなるので、
半分化粧をしているように見える
ことから
半分化粧→半化粧→【半夏生】に
変化したといわれています。
【半夏生】という呼び名は、
この薬草が生える時期から
きているといわれています。
【半夏生】は田植えが終わる
大切な節目になることから
青森県では【半夏生】を過ぎて
田植えをすると、
1日に1粒ずつ米の収穫が
減ってしまうという
言い伝えがあります。
この繁忙期を乗り切ると、
農家では田の神様を祭り、
麦団子やお神酒を供える習わしがあり、
農作物の無事を祝って物忌みをする
風習も残っています。
また
「半夏半毛(はんげはんけ)」
「半夏半作(はんげはんさく)」と
いう言葉も残っています。
意味は
「この日までに田植えを終わらせないと
秋の実りが遅れて半分しか収穫できない」
です。

3、半夏生の風習・行事食
【半夏生】は「物忌みの日」です。
そのため【半夏生】の日は
①働くことをなるべく控える。
②この日に穫れた野菜は食べない。
③井戸があれば蓋をする。
などの風習があります。
【半夏生】も他の「雑節」と同じように
「風習」や「行事食」があります。
以下に主なものを紹介します。
(1)新麦を神様に供えます
①麦が無事に収穫できたことに感謝。
(2)妖怪が徘徊する
①三重県の熊野、志摩地方では
「妖怪」が徘徊するとされ、
農作業を行う事への戒めになっています。
(3)ネギ畑へ入ることを忌避
①群馬県の一部での習わし。
農作業を行う事への戒めになっています。
(4)竹林に入ってはいけない
①埼玉県の一部での習わし。
農作業を行う事への
戒めになっています。
(5)タコ
①主に関西地方を中心に「タコ」を
食べます。
②「タコ」の足の
吸盤のように稲の根が、田んぼで
しっかり張るようにという
願いがこもっています。

(6)鯖
①江戸時代に福井藩主が
奨励したのが始まりです。
②夏までのスタミナ源として食べます。
(7)うどん
①【半夏生】の時期は「麦」の収穫が
終わる時期です。
②この時に収穫された「麦」で
うどんを打ち、
収穫作業を手伝ってくれた人に
振舞った事から由来しています。
③香川県の製麺事業協同組合が
1980年(昭和55年)に
7月2日を「うどんの日」に制定しました。
(8)きな粉餅
①主に奈良県で食べられています。
②無事に収穫できたことへの感謝のため
お供えし、食べました。
(9)芋汁
①長野県で食べられています。
②健康で夏を乗り切るために
食べられています。

4、おわりに
いかがでしたか?
【半夏生】について紹介しました。
【半夏生】の頃は、
本格的な夏の入り口です。
農家の方は勿論ですが、それ以外の方も、
ゆっくり休養して、
バランスの良い食事をして
英気を養って下さい。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
参考書籍:株式会社神宮館発行
暮らしのしきたり12ヶ月
美しい日本の歳時と年中行事
参考資料:ウィキペディア
広告
5、関連記事